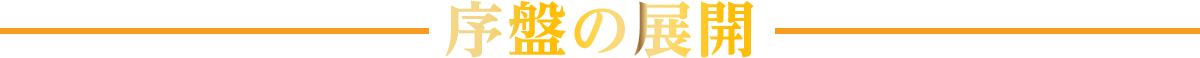タイムスケジュール オーディション 予選ラウンド 決勝戦 表彰式
特別ゲスト ぷろたん


 エンターテインメント
x
バスケットボール
常識を覆すルールで魅せる、新時代のショータイム。
観るだけじゃない、ファンが主役の参加型バスケが、ここに誕生。
エンターテインメント
x
バスケットボール
常識を覆すルールで魅せる、新時代のショータイム。
観るだけじゃない、ファンが主役の参加型バスケが、ここに誕生。


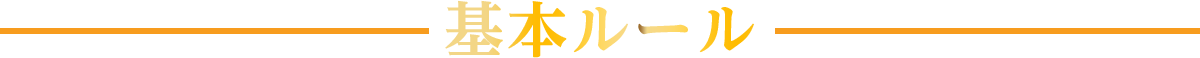
試合時間
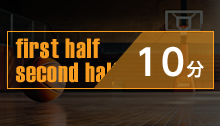 試合は前後半5分ずつの
合計10分
試合は前後半5分ずつの
合計10分
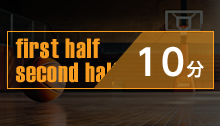 試合は前後半5分ずつの
合計10分
試合は前後半5分ずつの
合計10分
ティップオフ
 トスアップ時はエンドラインから同時にスタート
トスアップ時はエンドラインから同時にスタート
 トスアップ時はエンドラインから同時にスタート
トスアップ時はエンドラインから同時にスタート
ファウル
 ファウルは全てフリースロー(1点)
ファウルは全てフリースロー(1点)
 ファウルは全てフリースロー(1点)
ファウルは全てフリースロー(1点)
得点
 アークの中からのシュートは1点、外からのシュートは2点
アークの中からのシュートは1点、外からのシュートは2点
 アークの中からのシュートは1点、外からのシュートは2点
アークの中からのシュートは1点、外からのシュートは2点
ディープスリー
 ディープスリーは4点としてカウント
ディープスリーは4点としてカウント
 ディープスリーは4点としてカウント
ディープスリーは4点としてカウント

スター選手
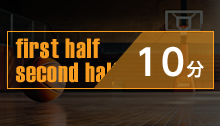 指定選手の得点はすべて「2倍」となる
指定選手の得点はすべて「2倍」となる
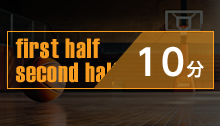 指定選手の得点はすべて「2倍」となる
指定選手の得点はすべて「2倍」となる
出場停止
 相手チームの任意の選手を退場させられる
相手チームの任意の選手を退場させられる
 相手チームの任意の選手を退場させられる
相手チームの任意の選手を退場させられる
1on1チャレンジ
 指名選手同士の1on1を実施
指名選手同士の1on1を実施
 指名選手同士の1on1を実施
指名選手同士の1on1を実施

オーナーチャレンジ
 サイコロの出た目の数だけオーナーがフリースローをうてる
サイコロの出た目の数だけオーナーがフリースローをうてる
 サイコロの出た目の数だけオーナーがフリースローをうてる
サイコロの出た目の数だけオーナーがフリースローをうてる
ファイナル2ミニッツ
 試合終了前の2分間はすべての得点が「2倍」
試合終了前の2分間はすべての得点が「2倍」
 試合終了前の2分間はすべての得点が「2倍」
試合終了前の2分間はすべての得点が「2倍」