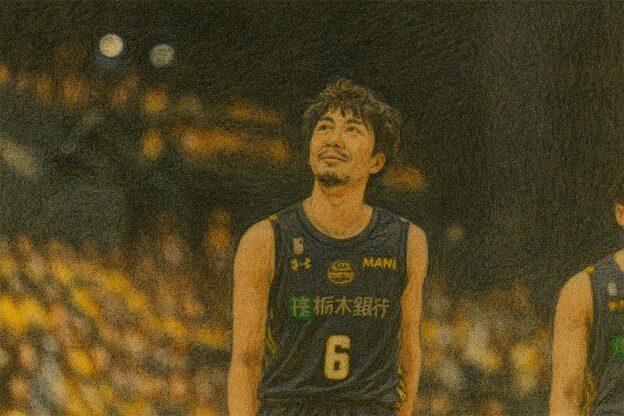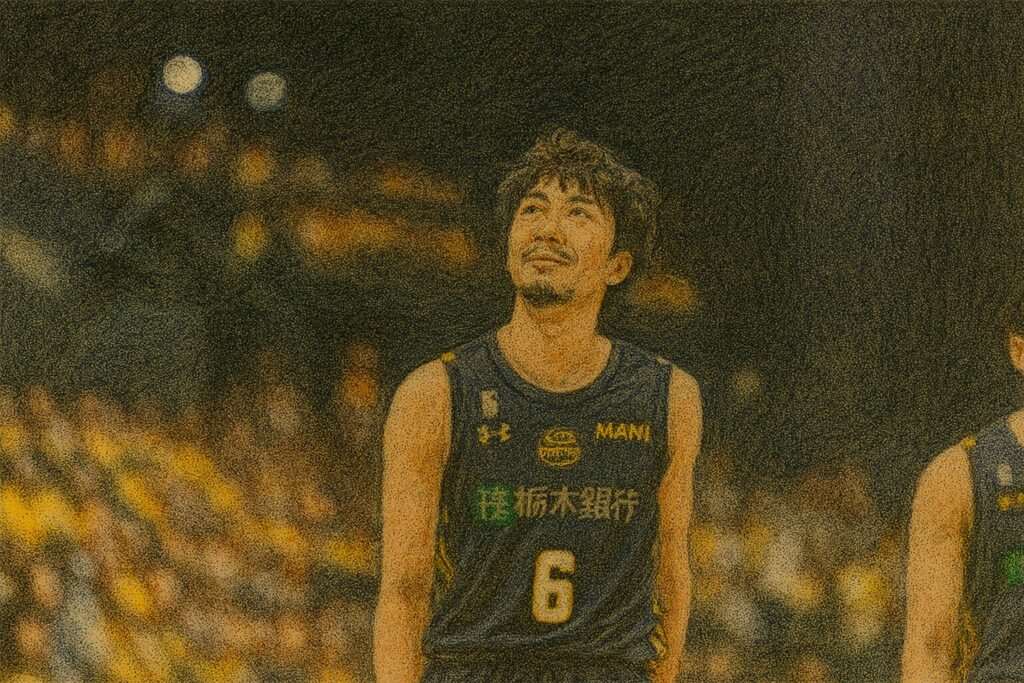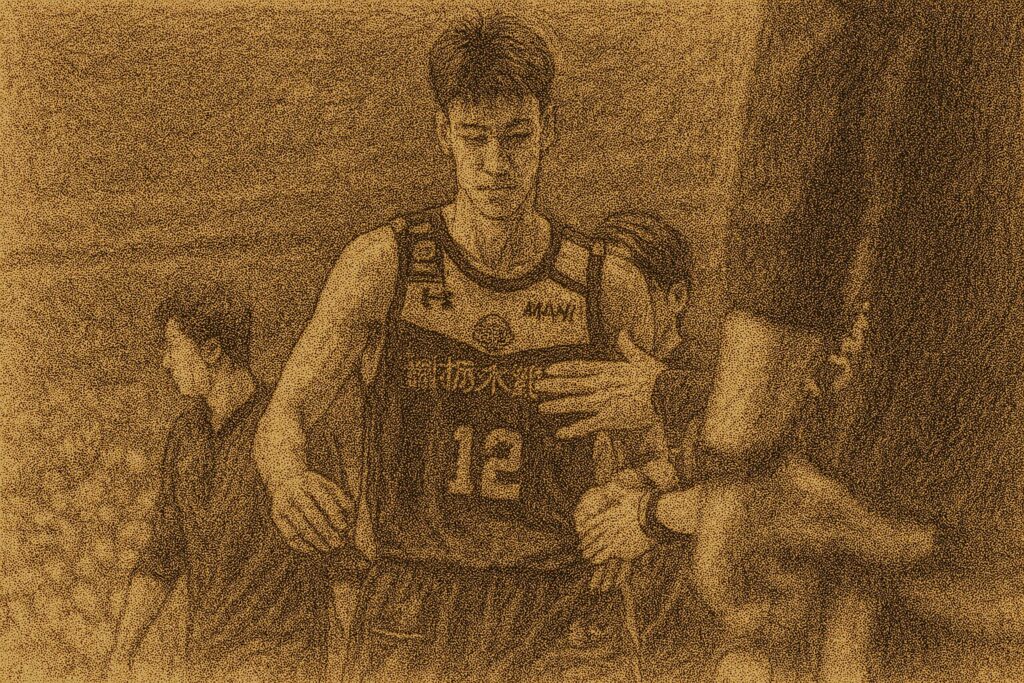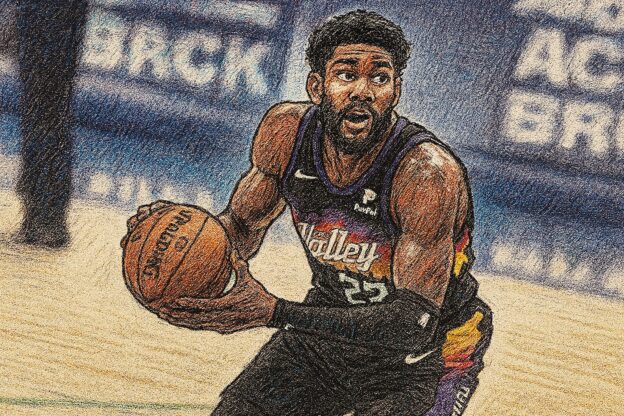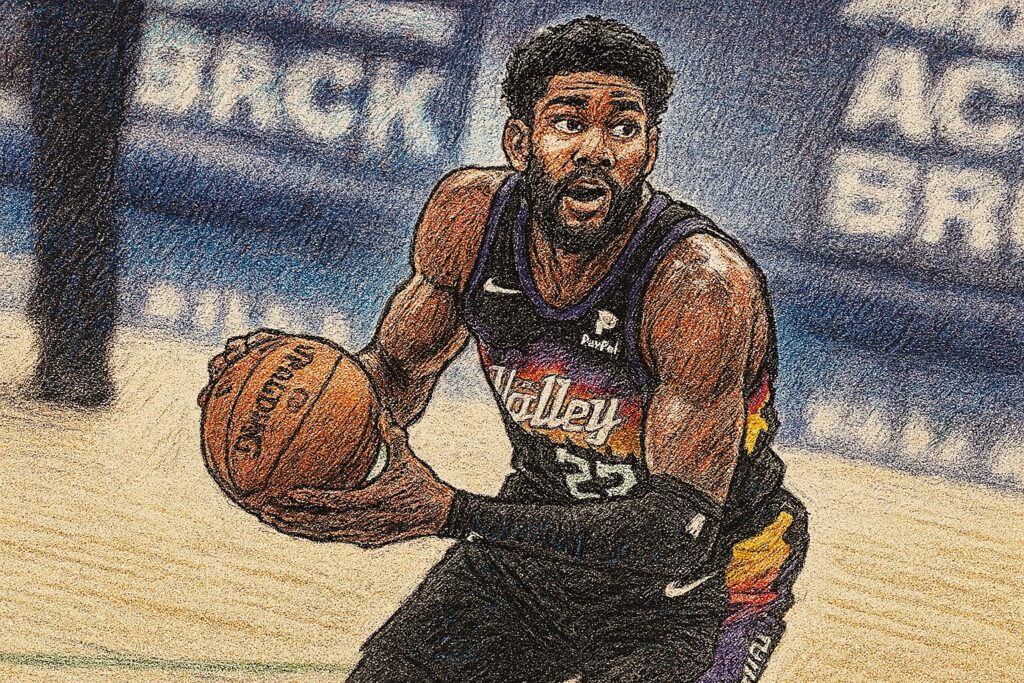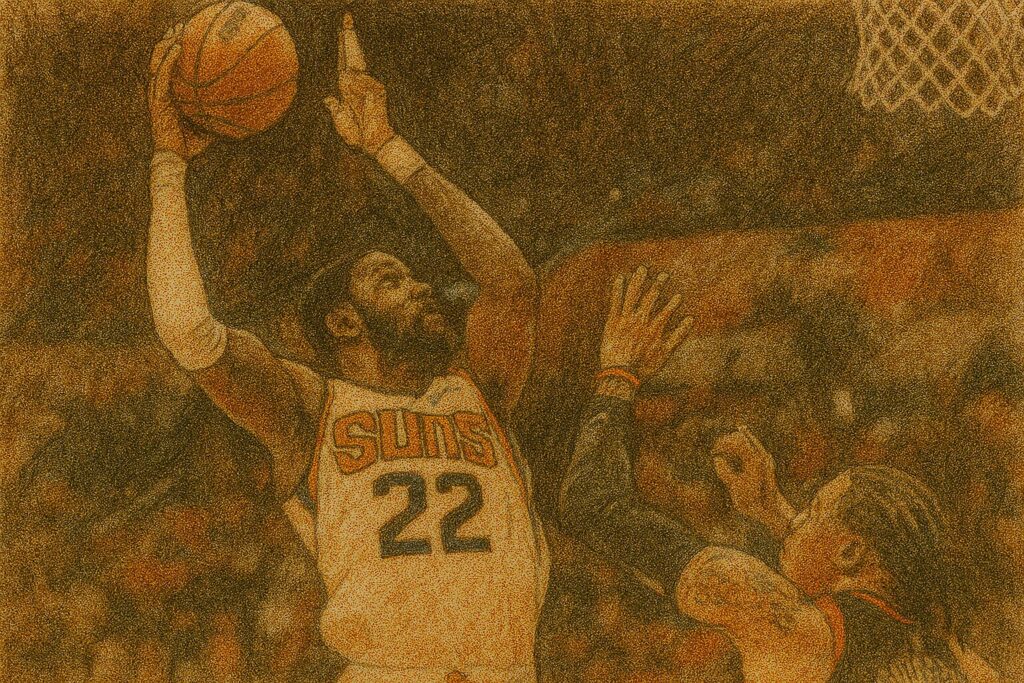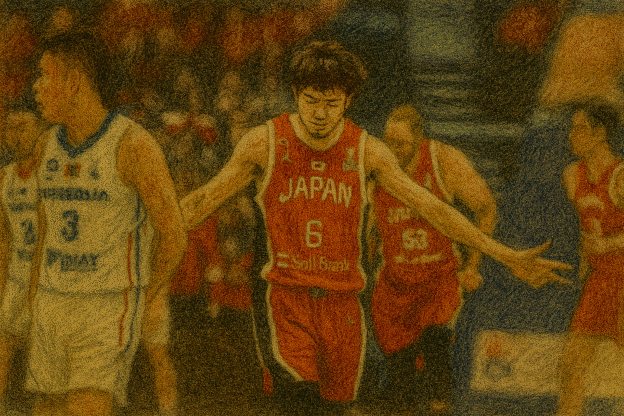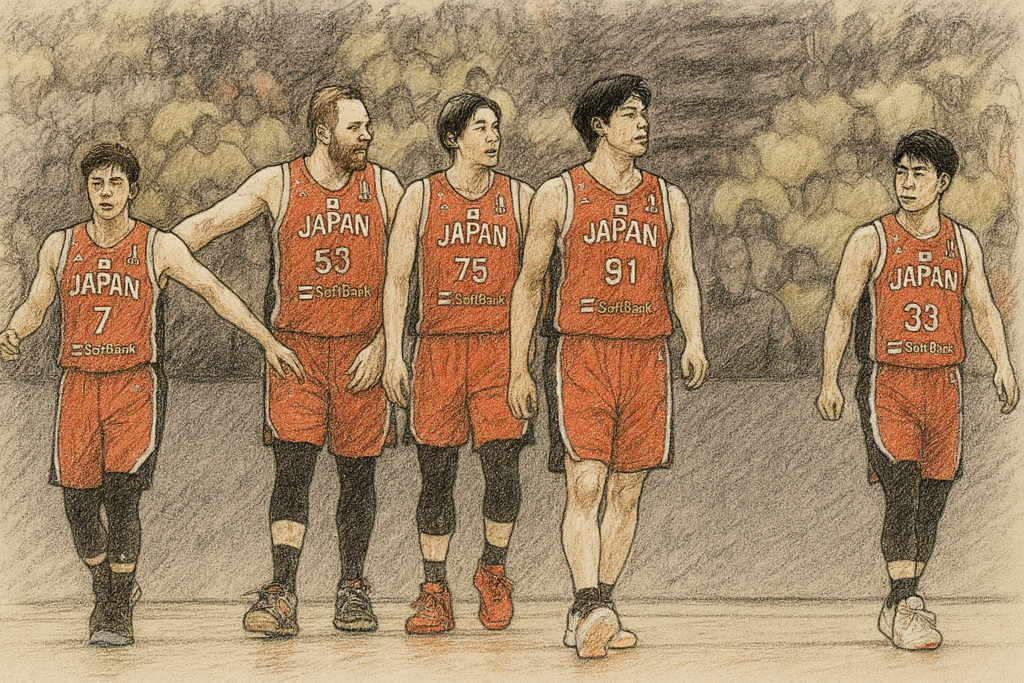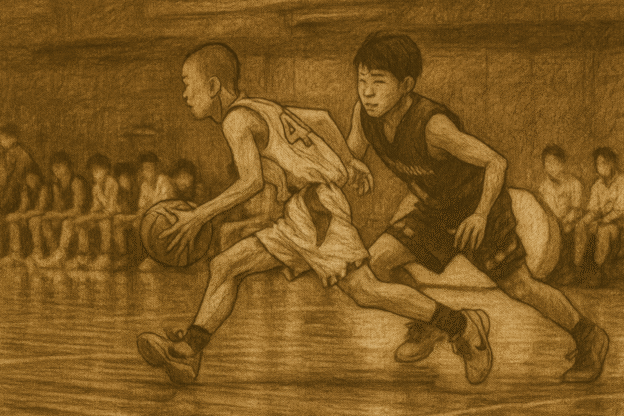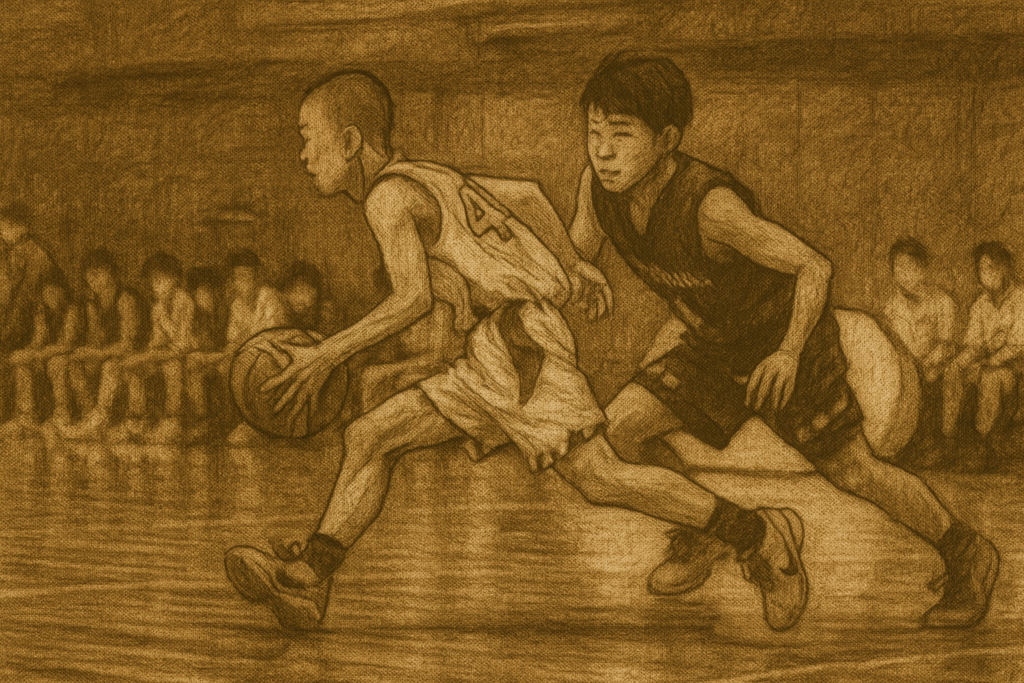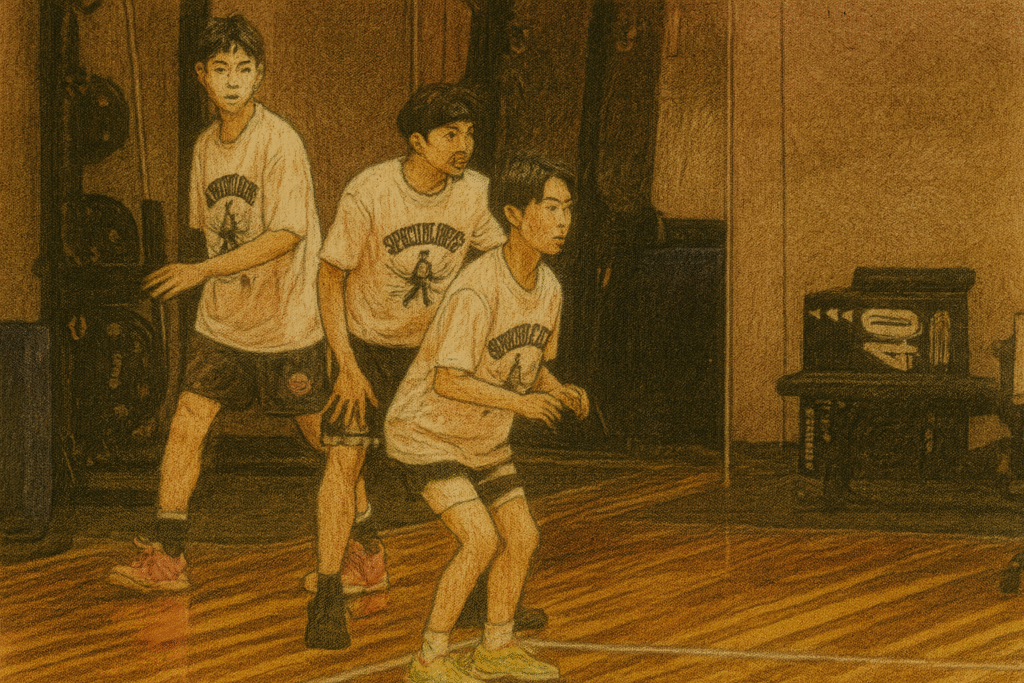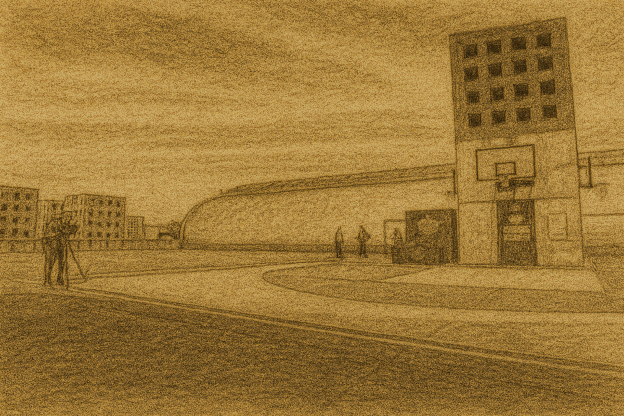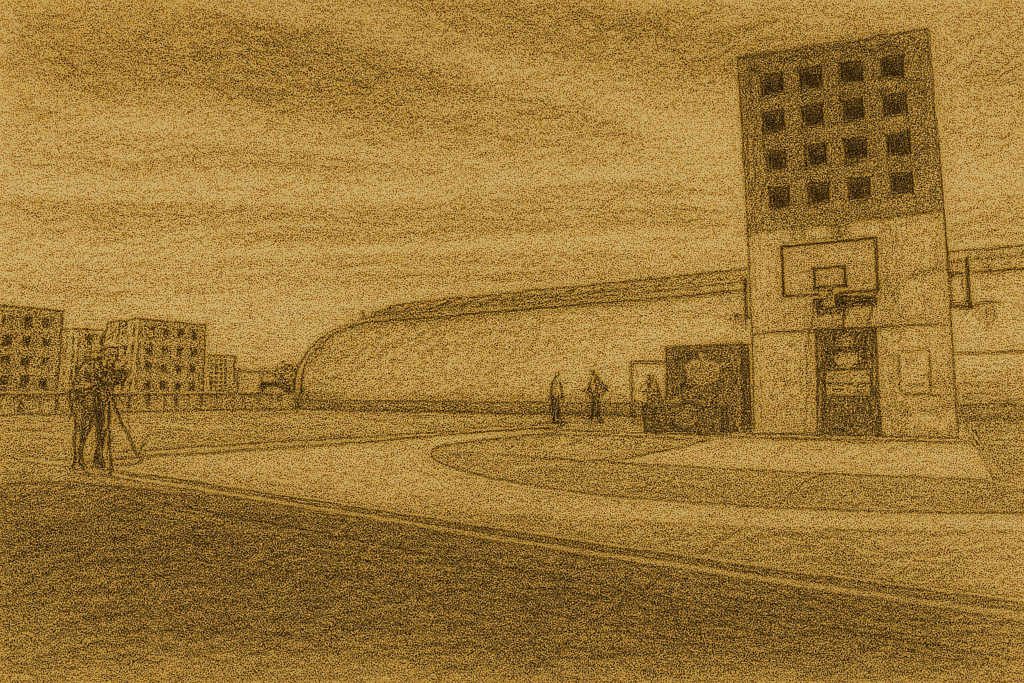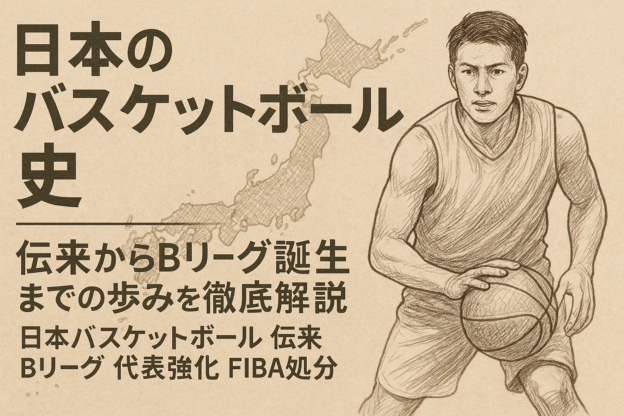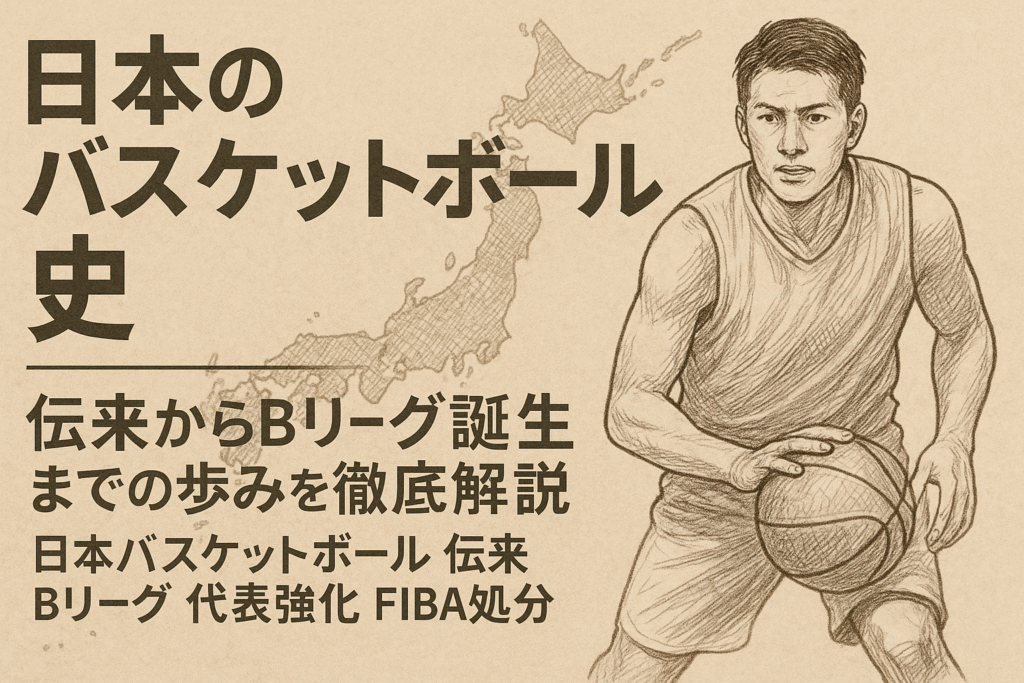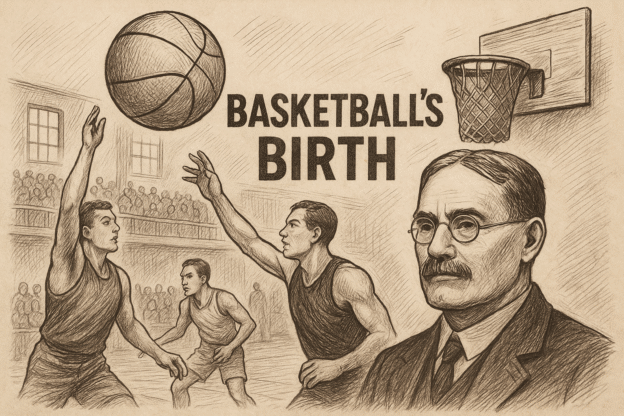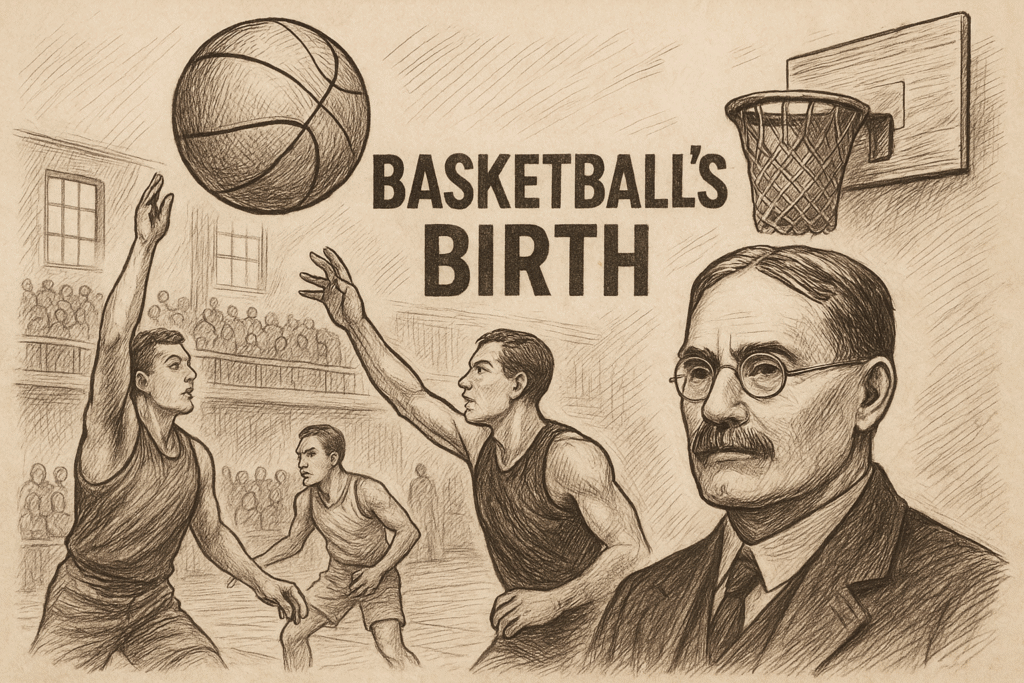女子ユニバ日本代表が発表、若手精鋭12名が国際大会へ
2025年6月30日、日本バスケットボール協会(JBA)は、「第44回ウィリアム・ジョーンズカップ」に臨む女子ユニバーシアード日本代表の最終メンバー12名を発表しました。チームは台北市で行われる本大会に続き、「FISUワールドユニバーシティゲームズ(旧ユニバーシアード)」にも参戦予定です。
平均年齢22.2歳、若手中心の編成に

小笠原真人ヘッドコーチの指揮のもと、今大会に臨む女子代表チームは、平均年齢22.2歳、平均身長174.3cmという構成。学生世代の注目株と、Wリーグで台頭する若手がバランスよく選出され、次世代の日本代表を担う人材が揃いました。
注目の選手:絈野夏海と佐藤多伽子

今回のメンバーで最年少となるのは、20歳の絈野夏海(東京医療保健大学2年)。173cmのシューティングガードであり、大学バスケ界でも高いスキルと実績を誇ります。
また、Wリーグのプレステージ・インターナショナルアランマーレにアーリーエントリーした佐藤多伽子も選出。176cmのサイズと得点力を備えたSGとして注目を集めています。大学とプロの経験が融合された彼女の活躍に期待が高まります。
Wリーグと大学バスケの融合が加速

この代表チームには、トヨタ自動車アンテロープスや日立ハイテククーガーズなどWリーグの強豪クラブに所属する選手が名を連ねています。学生バスケからプロステージへとステップアップした選手たちが融合し、競技力の底上げを図る構成です。
Wリーグの実戦経験を積んだ選手と、大学リーグのエースたちが共にプレーすることで、個人のスキルだけでなく戦術理解の深化も期待されます。
ジョーンズカップでの戦い、そしてドイツへ
ユニバ女子代表は、7月2日から台湾・台北市で開催されるジョーンズカップに出場。その後は、7月16日からドイツで開催されるFISUワールドユニバーシティゲームズにも連続して出場する予定です。
連戦となる国際大会で、若手選手たちはハイレベルな試合経験を積み、日本女子バスケット界の未来を担う存在へと成長していくことでしょう。
代表メンバー一覧(2025年6月30日発表)
- #0 山田葵(PG/167cm/富士通レッドウェーブ)
- #4 絈野夏海(SG/173cm/東京医療保健大学2年)
- #5 藤澤夢叶(G/162cm/山梨学院大学4年)
- #11 岡本美優(PF/179cm/トヨタ自動車アンテロープス)
- #14 朝比奈あずさ(C/185cm/筑波大学4年)
- #19 舘山萌菜(SF/177cm/日立ハイテククーガーズ)
- #25 佐藤多伽子(SG/176cm/プレステージ・インターナショナルアランマーレ)
- #30 三浦舞華(SG/170cm/トヨタ自動車アンテロープス)
- #42 田中平和(PF/180cm/トヨタ自動車アンテロープス)
- #45 粟谷真帆(PF/182cm/日立ハイテククーガーズ)
- #74 樋口鈴乃(PG/163cm/日立ハイテククーガーズ)
- #91 大脇晴(PF/178cm/東京医療保健大学4年)
今後の視聴方法と応援のポイント
試合の模様はJBAやFIBA関連の公式サイト、動画配信プラットフォームを通じて配信される可能性があります。日本の未来を担う若き才能たちが国際舞台でどのような戦いを見せるのか、バスケットボールファンにとっては見逃せない2大会となるでしょう。
将来の日本代表の中核を担うであろう12名の選手たちの成長と挑戦に、ぜひ注目してください。