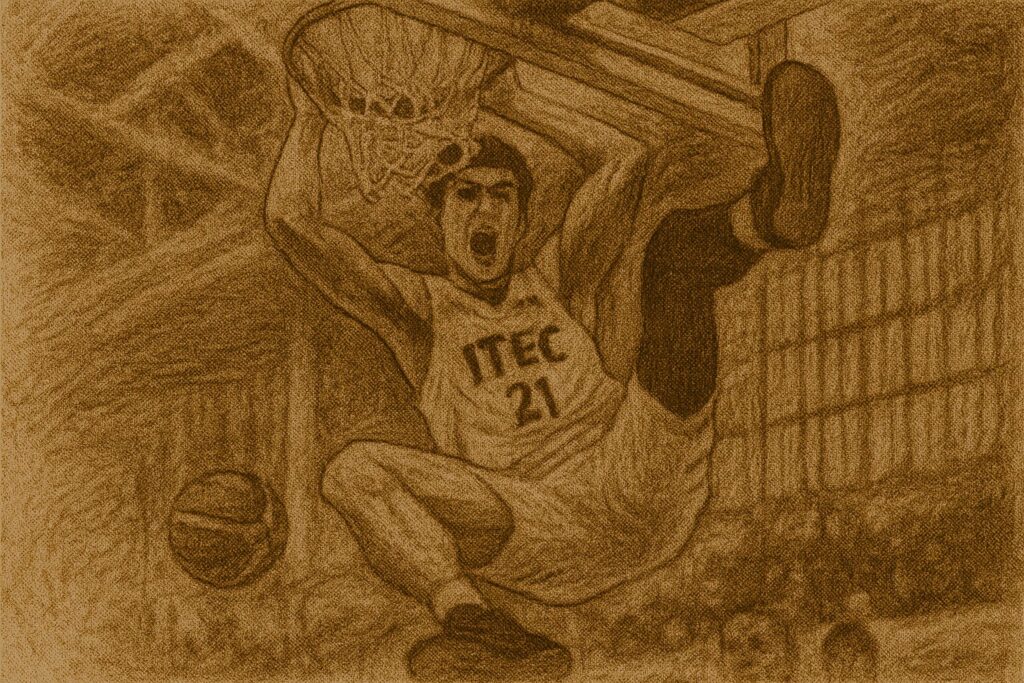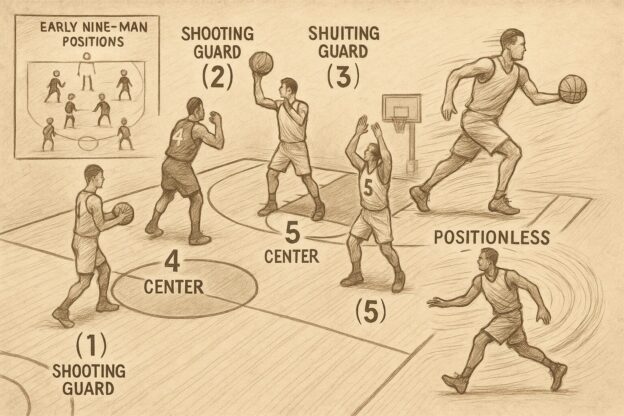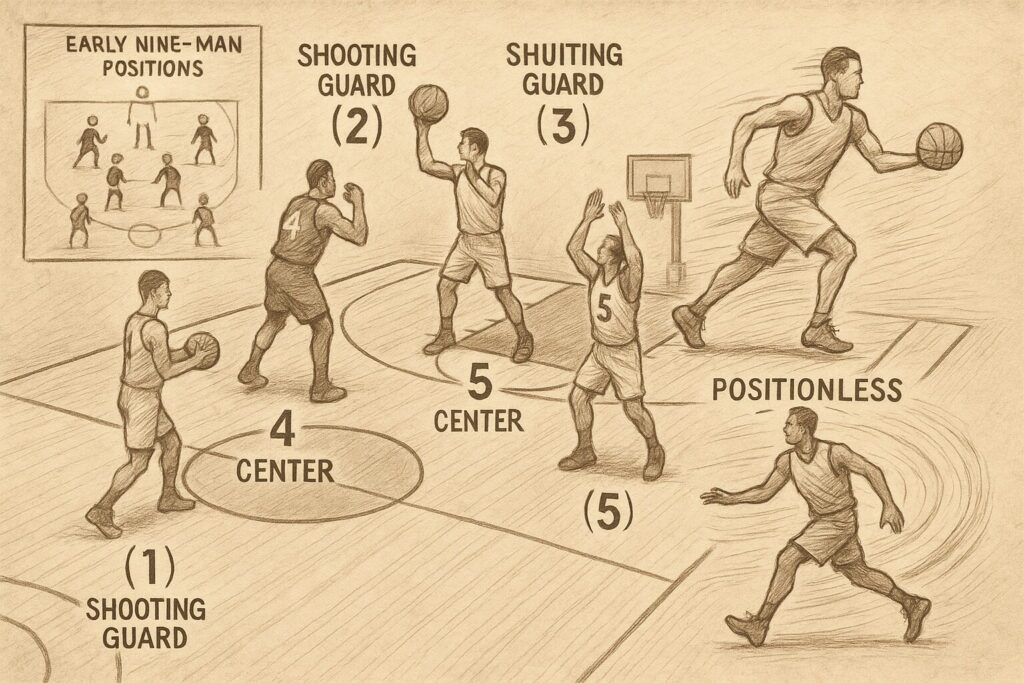7月7日Bリーグ契約情報:NBAドラフト3位指名のジャリル・オカフォーがレバンガ北海道へ、若手日本代表フォワードもB1参戦

2025年7月7日、Bリーグ所属クラブは、2025-26シーズンに向けた選手とコーチの契約情報を更新しました。この日発表された中でも、特に注目を集めたのは、レバンガ北海道のジャリル・オカフォー獲得のニュースです。さらに、秋田ノーザンハピネッツ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、福島ファイヤーボンズといったクラブの新規契約も発表され、注目の選手が続々とBリーグに加わりました。
ジャリル・オカフォー、レバンガ北海道に加入
レバンガ北海道は、NBAドラフト2015でフィラデルフィア・セブンティシクサーズから1巡目全体3位で指名されたジャリル・オカフォーを獲得したことを発表しました。オカフォーは、NBAでのプレー経験を持つビッグマンで、オールルーキーファーストチームに選ばれた実力を誇ります。彼の加入により、レバンガ北海道のインサイドがさらに強化されることが期待されています。
オカフォーは、これまでのキャリアで得た経験を活かし、Bリーグでの新たな挑戦を始めます。レバンガ北海道のGM、桜井良太は「レバンガ史上最高とも言える選手の加入」とコメントし、オカフォーの活躍に大きな期待を寄せています。オカフォーのインサイドでの支配力は、チームの攻守において重要な役割を果たすことは間違いないでしょう。
アリ・メザーが秋田ノーザンハピネッツに加入
さらに、秋田ノーザンハピネッツは、レバノン代表のアリ・メザーを獲得しました。メザーは、レバノンのプロリーグで長年活躍してきたポイントガードで、2024-25シーズンはB2リーグでも注目の活躍を見せた選手です。秋田ノーザンハピネッツは、アジア特別枠を活用してメザーを迎え入れ、さらなる戦力強化を図ります。
メザーは、今後のBリーグでもその得点力とゲームメイク能力を発揮し、チームに大きな影響を与えることが期待されます。彼の加入により、秋田ノーザンハピネッツのバックコートは一層強化され、より安定したプレーが可能になるでしょう。
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、一挙3選手の加入

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、ウィリアム・ジョーンズカップ男子日本代表の小澤飛悠や、NCAAディビジョン3のウィットワース大学でプレーしたジェイク・ホルツなど、今後のBリーグで注目される若手選手を3名加えました。
小澤飛悠は、特にそのスピードとディフェンス力が光る若手フォワードで、代表経験も豊富です。ホルツは、大学時代に活躍した実力派で、名古屋にとって今後の大きな戦力となることが期待されます。また、B3リーグでプレーした大型ガードの鎌田真も加わり、名古屋は新たな戦力を手に入れました。
福島ファイヤーボンズの新ヘッドコーチと選手加入
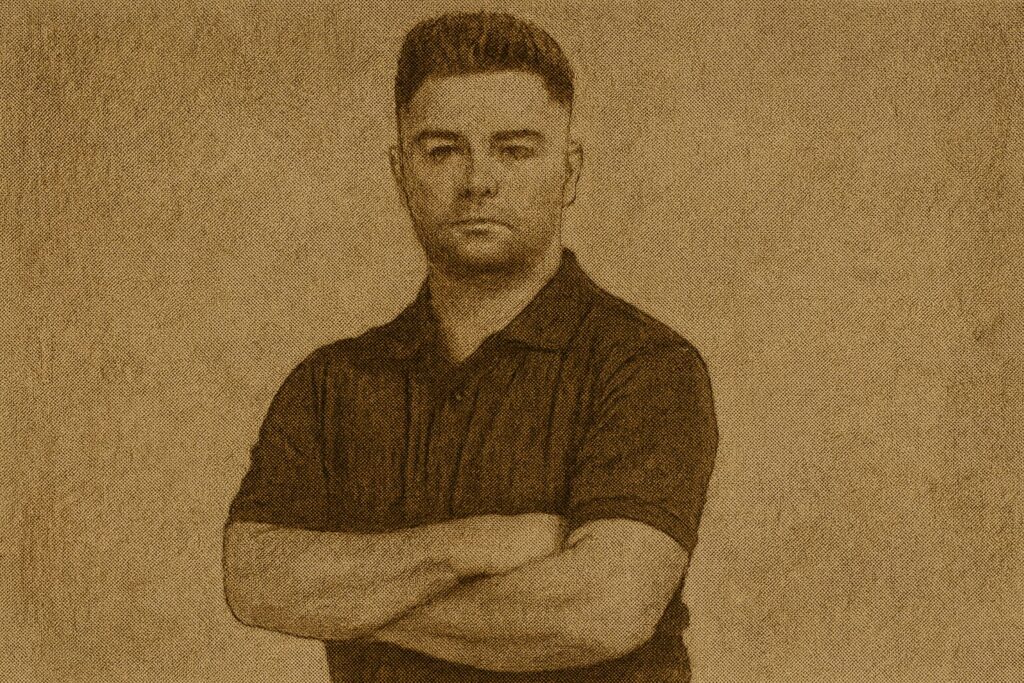
B2の福島ファイヤーボンズは、新ヘッドコーチとして、台湾リーグ王者のニュータイペイ・キングスを率いたライアン・マルシャン氏を招聘しました。マルシャンは、台湾リーグでの豊富な経験を持つ指導者で、福島の再建に大いに期待が寄せられています。
また、福島は得点源として昨シーズン活躍したケニー・マニゴールトも迎え入れ、さらなる戦力強化を図っています。ケニー・マニゴールトは、攻守両面でチームに貢献できる実力を持ち、福島の攻撃力を大いに引き上げることが期待されています。
7月7日のBリーグ契約情報一覧
以下は、7月7日に発表されたBリーグの契約情報の一覧です:
- 新規契約:ジャリル・オカフォー(プエルトリコ⇒北海道)、アリ・メザー(レバノン⇒秋田)、ジェイク・ホルツ(ウィットワース大学/NCAA D3⇒名古屋D)、小澤飛悠(日本体育大学⇒名古屋D)、ケニー・マニゴールト(台湾⇒福島)
- 移籍:鎌田真(湘南⇒名古屋D)、藤原瞭我(神戸⇒東京Z)
- 契約継続:エリエット・ドンリー(信州)
- コーチ:ライアン・マルシャン(福島/HC新規契約)、マーク・コッポラ(福島/AC新規契約)、輪島射矢(大阪⇒福島/AC新規契約)
今後のBリーグの注目ポイント
7月7日に発表された契約情報を見ても、Bリーグは着実に戦力強化を進めています。特に、ジャリル・オカフォーのようなNBA経験を持つ選手の加入は、リーグ全体のレベルアップに寄与するでしょう。さらに、若手選手たちがB1に挑戦する姿勢や、チーム全体のバランスを保ちながら進化する姿にも注目が集まります。
新シーズンに向けて、各クラブはより強固なチーム作りを目指し、戦力を整えています。これからのBリーグの展開に注目し、各選手の活躍を見守りましょう。
まとめ
7月7日の契約情報では、レバンガ北海道のジャリル・オカフォー獲得をはじめ、Bリーグに新たな才能を加える契約が発表されました。アリ・メザーの加入で秋田ノーザンハピネッツが強化され、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは若手選手たちを迎えてさらに強力なチームを作り上げました。福島ファイヤーボンズも新ヘッドコーチを迎え、今後の戦力が楽しみです。これからのBリーグの動向にも大いに注目しましょう。